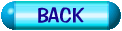19・温泉津温泉
|
すでに紹介しているとおり、ここ温泉津温泉には外湯が2つある。 一方薬師湯は、明治5年に発生した浜田地震の影響で、元湯の泉源とは別のところから湧き始めたのだそうだ。 薬師湯が別名「震湯」と呼ばれる所以である。 別の場所とはいっても近距離の両者、同じ湯が湧いているのかと思いきや、泉質は微妙に異なるらしい。 温度にもけっこう差があって、元湯のほうが薬師湯よりも高温という。 となると、温泉シロウトとしては、宿と同じ泉質の薬師湯をステップ1にさせてもらおう。 というわけでさっそく、丹前羽織って薬師湯へGO。 番台ではタオルや石鹸、シャンプーなどが買えるようながら、持ち込みももちろん可能だ。 宿からメインストリートに出れば、もうそこが薬師湯だ。
毛利元就の命で沖泊の管理運営責任者になった、内藤内蔵丞のご子孫が湯元管理人になっている、という話はすでに触れた。 現在温泉として利用されているのは新館で、奥側の建物は大正時代に建てられた旧館だ。
旧館は現存する温泉施設としては温泉津最古の建物だそうで、大正8年に建てられたものだというから、出雲の旧大社駅よりも古い。 博物館か何かになっているのかと思いきや、現在は大正モダンの姿をそのままに、震湯カフェ内蔵丞という名のステキなカフェとして人気を呼んでいるという。 そのカフェの人気メニュー奉行めしや地元食材を使っているというカレーを、素敵な内装ともども是非味わってみたかった。 ああしかし、滞在予定中唯一昼食時間帯があるこの日は、このお店の定休日、木曜なのであった(涙)。 カフェは休みでも、温泉は年中無休。 入り口から男女に分かれており、真ん中に番台があるというスタイルは、懐かしい方には懐かしいことだろう。
でも寒い季節だからか、料金450円の支払いは中に入ってからということになっていた(番台はそのまま中に通じている)。 番台そばにある下駄箱にサンダルを入れ、引き戸を開けると…
いい感じに庶民派の佇まい。 一見銭湯の脱衣所のようながら、温泉だけに注意事項がいろいろ書いてある。 それによると、入り方のおすすめとして、3分湯に浸かっては湯船から出て、体を洗うなり洗髪するなり時間を空けてから湯船に入り、また3分ほどしたら外に出て休憩し…というように、小刻みに入りなさいという。 そしてそれを繰り返しているうちにやがてジワジワと額に汗が浮かぶくらいになれば、一丁上がりなのだそうな。 そうしているうちに体の水分が失われていき、血液がドロドロになってしまうので、それを防止するためにも、写真奥に見えるイオン水をコップで1杯飲んでからどうぞ、とも書かれてあった。 抗菌生活押しの今の世の中では珍しい、コップ共同使用が微笑ましい。 素直なワタシは、とりあえずコップ一杯飲んでおいた。 ここから湯の供給を受けている各旅館の内湯ほどではないにしろ、そもそも湧出量が湯水のようではないだけに、それほど大きくはない湯船はこんな感じ。
写真手前側にシャワーやカランがあり、湯桶や風呂椅子が並べてある。 このように他に誰もいないということは平日でもそうそう無さそうなほどに、入浴客は途絶えなかった。 湯元から湧き出ている湯は透明なのだそうだけど、湯船に溜まると得体のしれない何かの力を湛えているかのような緑色になる。 かけ湯を済ませ、まずはチャポンと湯船に浸かる。 おお、個人的にかなり適温かも。 沖泊では鼻ぐり巡りをし、そこからさらにやきものの里までグルリと歩いた体に溜まった疲れが、湯船にジッとしているだけでジワワワワワワ〜ンと滲みだしていく。 このジワワワワ〜ン、どんなに効能がある温泉であろうとも、肉体的疲労がないと思う存分味わえない(※個人の感想です)。 湯温の差こそあれ、泉源が同じだけに、なかのや旅館さんの内風呂同様鉄分の香りがして、味は塩辛い。 注意書きに従いつつ、入っては休み入っては休みを繰り返しているうちに、体の奥の奥まで暖かなものに包まれていくような気がしてきた。 母鳥に温めてもらっている卵って、こんな気持ちなんだろうか……。 こういうのを、芯から温まるっていうんだろうなぁ。 シロウトなので注意書きどおりに出入りを繰り返しているワタシとは違い、常連さんたちはきっと気にしない…… …のかと思いきや、シャンプー・石鹸タオルその他温泉マイギヤセット持参のベテラン常連さんらしき方も含め、みなさんちゃんと休憩を間に挟んでおられた。
温泉によっては、その泉質ゆえに上がる前にシャワーでお湯を流せとアドバイスするところもある。 それによってお肌ツルツル効果が、相乗的にパワーアップするらしい。
お肌ツルツルに興味はないけれど、あまりにも酸性の湯の場合、本気で湯をシャワーで流さないと、そのあと着た衣服がボロボロになってしまうなんてこともあった。 相当温まったので、そろそろ上がることにした。 実はここ薬師湯の楽しみは、入浴だけではない。 この風呂場を出たところにある階段を上がって3階まで行くと、サービスのコーヒーマシンがあって……
紙コップに入れたコーヒー片手に、2階にあるロビーでくつろげるのだ。
我々が来る前からくつろいでおられた年配のご婦人は現在療養中とのことで、お医者さんに強く勧められたこともあって、車で15分の距離を足繁く通うようになられたのだとか。 おかげで体調抜群で、やめられないとまらない状態になっているそうな。 ここでくつろいだ後、3階の屋上テラスに出てみた。 ここからの眺めは、ある意味温泉津温泉の象徴のひとつかもしれない。
石州瓦の赤い波、そして旧館の屋根に聳え立つ2つの塔。 そこだけ見れば、まるで日本じゃないどこかの国のようですらある。
……そこまではワタシも思ったけれど。 このテラスに出るドアに貼り付けてあった説明書きは言う。
「島根のフィレンツェ」はいくらなんでも……。 フィレンツェには行ったことがないのでその真偽のほどは不明ながら、たしかにこの尖塔と赤い瓦が日本離れしていることはたしかだ。 この尖塔が、なかのや旅館さんの前からの眺めの中でも聳え立っている。
湯治場の路地からフィレンツェが見える……? 湯と眺めを堪能した薬師湯をあとにし、いったん宿で休憩した後、再び温泉を心行くまで味わえるよう、午後の歩け歩けに繰り出した。 歩け歩けから帰ってきたあとは、今度はステップ2、元湯初探訪といこう。 薬師湯までなかのや旅館さんから歩いて1分なら、元湯までは1分30秒くらいで到着。
丹前を羽織る程度の軽装でも、寒さを感じる前に到着する近さである。 前述のとおり元湯は、タヌキが傷を癒していた頃から湧いていた大昔からの泉源だ。
元湯、元湯とみんな読んでいるようながら、温泉としての正式名称は泉薬湯(せんやくとう)というそうな。
元湯というのは、薬師湯(当初は藤乃湯といったらしい)が新たに誕生したあと、新しい湯、すなわち新湯に対する呼称なのだそうである。 しかしここで注目すべきは、正式名称の看板ではなく、そのうえにある彫刻なのだそうな。 湯をいただいた後、元湯の佇まいの写真を撮ろうとしていると、番台のおばちゃんがこれを撮りなさい、あれを撮ったらいいよ、といろいろとアドバイスしてくれたひとつでもあるその注目すべきところとは、これ。
たぬたぬ! さすがタヌキ発見伝説の温泉、看板にタヌキが。 現在のコンクリート造りの建物がいつの頃からなのかは知らないけれど、江戸の昔にも看板にタヌキがいたのだろうか。 元湯は薬師湯と同じく入り口で男女に分かれており、番台が中央にある。 料金350円を払って中に入ると下駄箱があり、そこで靴を脱いでさらに奥の引き戸を開ける。
写真を撮っているワタシの背後には、脱衣用ロッカーの他に、地元の常連さんのためのマイ温泉ギヤセット置き場の棚があって、個人個人の温泉入浴セットがビッシリ置かれてあった。 浴室に入ると…
温泉成分が析出して床は茶色く染まり、湯口はもはや原形をとどめず、宇宙生命体の肌のようにゴツゴツ化している。 外見はコンクリート造りながら、中は往時を彷彿させる雰囲気に満ち満ちていた。 湯船は3つにセパレートされていて、左端が「座り湯」(水深が腰までくらいしかない)、中央が「ぬるい湯」、そして右端が「熱い湯」と書かれた札が壁にある。 源泉から届くかけ流しの湯は「熱い湯」に景気よく注ぎ込まれている。 「ぬるい湯」と「座り湯」の境界はステンレスのパイプだけなので、湯温はほぼ同じだ。 水道の流しはあるけれど薬師湯とは違ってシャワーやカランの設備はないから、シャンプーや石鹸を使う方は各自脇でやることになる。 一応入浴時の注意書きでもそのように触れられてはいるのだけれど、そうするといちいち湯を汲むのに歩いて行かなきゃならないからか、常連さんなどはまったく頓着することなく、湯船の脇で景気よくバシャバシャやっていた。 ともかくもかけ湯をしてから、とりあえず「ぬるい湯」に入ってみる。 ああ……いい感じ。 これでもワタシには充分すぎるほどの温度なのだけど、先客のなかには、まるで修行でもしているかのように、「熱い湯」に浸かっている人がいる。 湯から上がる彼らの背中は…いや、全身は、茹でたタコなみに赤い。 「ぬるい湯」で体が充分温まったのを見計らい、境界越しに「熱い湯」に腕だけ浸けてみた。 熱ッ!! まるでスーパージョッキーの熱湯CM。 薬師湯同様ここでも3分毎くらいに休憩を挟むことを奨励されているけれど、言われなくても3分以内に出なきゃヤバそうなほどだ。
でもこのガツン!とくる熱さを求める人は多い。 「元湯に入ってきました!」 と、先ほどまで着ていた背広を肩にかけ、気持ちよさげに帰っていった。 昔ながらの常連さんも多いらしく、 「今日は熱くないね」 などと言っているおじぃもいた。 日によって湯の加減が違うのだそうだけど、これで熱くないって……本気出したらどうなるんだろう? 常連さん同士っぽい年配の方々がお話されているのをうかがっていると、食欲減退気味のときに湯に浸かると、あっという間に食欲増進するという。 やっぱそうだよなぁ、腹減るものなぁ。 その他いろいろ体にいいことずくめのようで、身近にこんな温泉があれば、さぞかし寿命も延びることだろう。 何度も湯船の出入りを繰り返しているうちに、体はポカポカになってきた。 そろそろ限界を迎えたところで、元湯初探訪終了。 外に出て写真を撮ろうとしていると、番台のご婦人にアドバイスをいただいた、ということはすでに触れた。 元湯の正面にあるアヤシげな龍の像もそのひとつ。
これが、温泉を飲むことができる設備であることを教わった。 元湯温泉さんが管理しているものらしい。 この龍の像にあるヒミツのボタンをポチッと押すと……
龍の口から温泉がピューッ! 備え付けのカップに注いで飲むようになっている。
ずっと出しっぱなしにしているとやがて熱い湯が出てくるそうながら、そうしてもいられないからすぐにカップに注いだものを飲んでみると、これがまた不思議的テイスト。 翌朝、朝6時過ぎにもう一度元湯に入りに来た。 朝は体が冷えきっているからか、「熱い湯」はよりいっそう熱く感じられた。 でもものは試しとばかり、片足をグンと突っこんでみたら…… やっぱり熱ッ!! 絶対無理。 よくもまぁみなさん入れるよなぁ…。
薬師湯は土日祝は朝6時から開いているけど、平日の朝は8時から。 なので6時過ぎに行くと、一番風呂を求めて常連さんが数名いらっしゃった。 彼らがしばらくすると風呂から上がるので、貸し切り状態になる時間帯がある(湯船の写真はこの時にパシャ)。 レトロ感極まれりといった風情の湯治場の温泉で、貸し切り状態で朝湯に浸れるこのシアワセ……。 湯治場とはよく言ったもので、連日こうやって過ごしていれば、ストレスフリーで体の不調もあっという間に消えていくことだろう。 ただしほどほどにしておかないと、あまりにも心地よすぎて社会復帰不能になるかも。 前日も来たことを覚えていてくれた番台のおばちゃんが、お願いしたわけでもないのに、我々二人の写真を建物バックで撮りましょうといって、寒い朝に番台からわざわざ出てきて撮ってくださった。
今回ワタシが写っている唯一の写真だ。 1300年もの昔から湧き出ていた温泉津温泉は、噂にたがわぬ素晴らしいお湯だった。 歩き回って疲れたからこそ温泉に入ってダハー………となっているというのに、オタマサなどは温泉に入ったら疲れが取れた!とか何とか言って、再び夕方の散歩に出かけたほどだ。 絶景の露天風呂だとか100人くらい入れる大きさだとか、そういった温泉施設の華麗さ、豪華さ、近代的な美麗さを求める向きにはいささか系統が違うかもしれない。 けれどなにはさておいても湯の力を求める方なら、薬師湯、元湯ともどちらも大満足必至の、力漲る温泉だ。 これがホントのパワースポットである。 |