●海と島の雑貨屋さん●
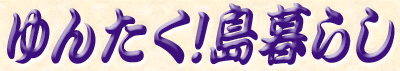
写真・文/植田正恵
●海と島の雑貨屋さん●
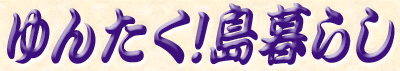
写真・文/植田正恵
月刊アクアネット2025年9月号
コロナ渦中、屋外で楽しめる遊びの一つとしてキャンプが流行り、キャンプ用品が飛ぶように売れたそうな。コロナ後の今も、その流れは続いているという。
水納島の浜にウミガメが産卵のために上陸する、という話を初めて耳にした学生時代、ただちに水納島カメパトロール計画を立てた。当時は片道30分かかったポンポン船(船賃は今の3分の1ほどだった)で島に上陸し、日中は島でスノーケリングを楽しみ、夜間はウミガメパトロールをして、運が良ければ産卵の様子を観察しよう、という計画だ。
島には当時から民宿があったとはいえ、貧乏学生にその予算があるはずはなく、宿泊場所はもちろん海岸だ。今風にグッズを揃えればキャンプといえるかもしれないけれど、装備的には完全に野宿である。
島にはコンビニはおろか商店すらひとつも無いことは知っていたから、食料は適当に買い出して持ち込み、トイレもシャワーも海で済ませ、眠くなったら砂浜の上でゴロリという、はたしてそれを「計画」と呼んでよいものかどうか今なら疑問に思うところではあっても、学生ならそれが当たり前だと当時は思っていた。
もっとも水納島には海水浴客用の公設のトイレとシャワーがその頃からあったおかげで水の確保は容易で、思いがけず夜間も使用できたので(当時)、かなりハイグレードな「野宿」ではあった。
埼玉の実家すぐ近くの河原に掲げられていた看板。春に帰省した折に弟に聞いたところによると、昔は週末にひと組ふた組がBBQをしている程度だった河原に大勢押し寄せるようになり、マナーの悪さが目立つようになってしまっては、行政としても対応せざるを得なかったらしく、当初は「直火禁止」だったものが、やがてBBQそのものが禁止になってしまったようだ。そのため昔からBBQ場として利用していた近隣住民の弟一家でさえ、友人を呼んで河原でBBQをするためには、駐車料金を取られるBBQ可能エリアまでわざわざ足を伸ばさなければならないという。自由に焚火すらできないということは、当然キャンプもNGなのだろう。目に余る『やりたい放題』のために、気がつけばいつの間にかまことに不自由な社会になっているのだった。
私自身が水納島に引っ越してきてからしばらくは、夏の週末にはビーチパーティーがてら海辺でキャンプをする人をよく見かけたし、ひと月以上も一人でキャンプをしている間にビーチスタッフとしてスカウトされ、気がつけば日中はパラソルを立てて働くようになっていたキャンパーもいた。
ところがここ10年くらいだろうか、夜釣りを楽しむ方々が桟橋上で簡易テントを張っていることはあっても、いわゆる「キャンプ」で島に滞在している方をほとんど見かけなくなった。世間ではぼっちキャンプが依然人気らしいというのに、これはいったいどうしたことだろう。
チラッと調べてみたところ、沖縄の海岸では焚火が禁止されているわけではないものの、人の手で管理がなされているところではほぼ直火が禁じられており、焚火をする場合は焚火台を用いることを条件にしているところが多いようだ。
なんでもそうだけど、流行することによって利用者が多くなり、分母が増えるとともにノーマナーな方々も増えてきて、行政もしくは地域が釘を刺さなければならなくなる、というパターンなのだろう。
いずれにせよ水納島の場合、車で現場に乗りつけて気軽にキャンプ、というわけにはいかないから、なんでも手軽が好まれるこのご時世では、わざわざ大きな荷物を抱えて連絡船に乗り、さらに海岸まで歩いてまでしてキャンプなどしたくない…ということなのかもしれない。
なにごとも過ぎたるは及ばざるがごとし、流行するのはいいけれど、世界が讃える日本のサポーターとは真逆の精神で現場を荒らす人が増える一方となれば、そりゃ目も当てられない惨状になるのは想像に難くない。
ルールを厳しくしなければ、とてもじゃないけれど美観を維持できなくなるのだろう。
やがてBBQもキャンプも、許可され管理された場所でしかできないがんじがらめのレジャーになってしまい、すでに今の子どもたちが「キャンプ」という言葉に抱くイメージは、その昔我々が幼かった時代のそれとは随分違ったものになっているのかもしれない。